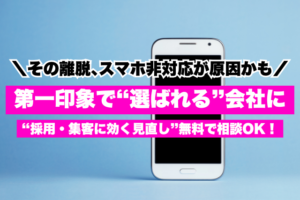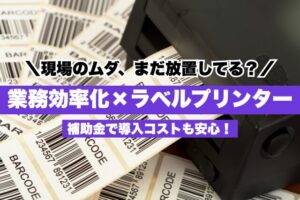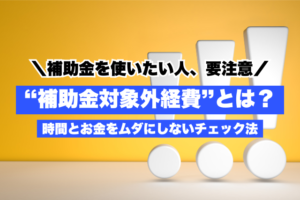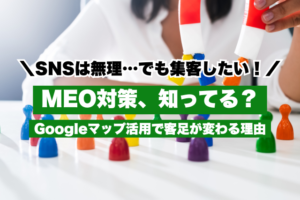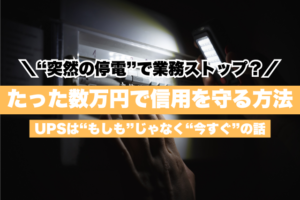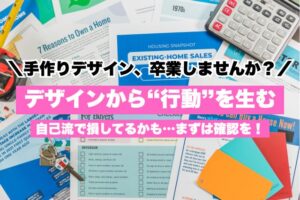FAXを残すべきか?やめるべきか?2025年版・中小企業のための判断軸
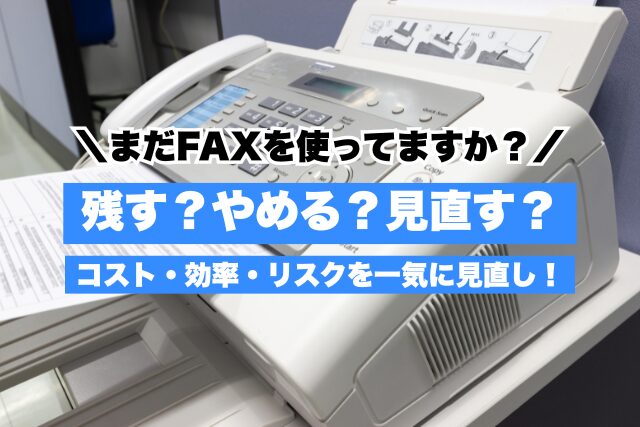
2025年現在、DX(デジタルトランスフォーメーション)やペーパーレス化が加速する中で、「まだFAXを使ってるの?」という声を聞く機会も増えました。
しかし、実際の現場では「FAXを使い続ける理由」や「やめたくてもやめられない事情」が根強く残っているのも事実です。
中小企業や個人事業主の皆さまにとって、FAXの扱いは「時代遅れ」ではなく、実務に即した合理的な判断が求められるテーマです。
今回は、FAXを残すべきか、やめるべきか、その判断軸を2025年の最新動向を踏まえて解説します。
FAXを残すべきケースとは?
以下のような条件に当てはまる場合、FAXを無理にやめるよりも、残した上で運用効率を高める方が現実的な選択となることがあります。
- 取引先がFAX対応しかしていない(例:医療・建設・卸売など一部業界ではFAX文化が根強く残っている)
- 社内のワークフローがFAX前提で構築されている(業務フローの大幅変更が必要になる)
- FAX内容をすぐに紙で回覧・保管する文化がある
このような場合、無理に廃止しようとすると、業務負担がかえって増えることもあるため、段階的な移行や代替手段の併用が現実的です。
FAXを廃止すべきタイミングとは?
一方で、以下のような状況ではFAXを思い切ってやめることで、業務効率の改善やコスト削減のメリットが大きくなります。
- ペーパーレス化やクラウド共有が社内に浸透している
- FAXの送受信が月数回程度しかない(ほとんど使用されていない)
- 複合機や電話回線の見直しを検討中(入替の好機)
FAXの使用頻度が減っている企業では、「とりあえず残しているだけ」の状態になっていることも。
この状態こそ、実は見直しの好機です。
「やめたいけどやめられない」…そんな現場の声も
私たちが支援している中でも、FAXに関する相談は年々増えています。
ただし、「やめた方がいいのはわかっているけど、どこから手をつければ…」という悩みも非常に多いです。
実際、FAXの運用には以下のようなコストと手間がかかっています:
- 紙代、インク代、保守費用などのランニングコスト
- 受信書類のスキャン・配布・保管にかかる作業時間
- 受信漏れ、送り間違いなどの人的ミスリスク
これらは「目に見えにくいコスト」であり、日々の業務に埋もれがちですが、見直すことで月間数千円〜数万円の改善につながるケースもあります。
進化する「代替手段」も選択肢に
最近では、従来のFAX番号をそのまま使いながら、ペーパーレス化を実現できる方法も登場しています。代表的なのが以下のようなものです:
- インターネットFAX(eFaxなど)
→ メール感覚でFAXを送受信可能。紙が不要に。 - PDF送信+共有クラウド
→ 取引先がメール対応であれば、クラウド共有で完全ペーパーレスも可能。 - 複合機の自動スキャン連携
→ 紙で受信したFAXを自動スキャンして社内共有サーバーに保存。
このように、完全にやめなくても「使い方を変える」選択肢があることも、今の時代ならではのポイントです。
複合機の見直しや回線整理とセットで考えるのが◎
FAX単体ではなく、コピー機の更新や通信回線の見直しのタイミングで同時に見直すことで、全体最適が実現しやすくなります。
たとえば…
- FAX機能付きの複合機を撤去し、インターネットFAXへ移行
- 電話回線を統合・整理し、通信費削減
- クラウド連携型複合機へ切り替え、業務効率を向上
このように設備投資+業務改善+補助金活用をセットで進めると、大きな効果が見込めます。
まとめ:FAXをなくすか、使い方を変えるか
FAXの見直しに正解はありません。
大切なのは、自社の現状に合った「無理のない移行」や「最適な運用ルール」を整えることです。
ファミリアジャパンでは、FAXの現状診断から代替手段のご提案、補助金を活用した複合機入替まで、一括でサポート可能です。
「今すぐやめられるかは分からないけど、見直したい」
そんな段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。